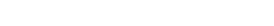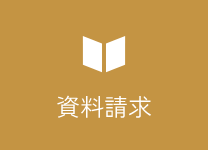2025/10/13
大人の社会見学 国立科学博物館
先日、久しぶりに上野を訪れました。目的は、ずっと気になっていた「かはく」(科博)へ。
以前、テレビ東京のソロ活女子のススメで見て以来、ずっと行ってみたいなぁと思っていた場所。
なかなかタイミングが合わなかったのですが、子どもたちに話してみると意外にも乗り気で、一緒に出かけてきました。

まず訪れたのは、地球の歴史と生命の歩みをテーマにした「地球館」。
ここでは、地球誕生から現在までの46億年を壮大なスケールでたどることができます。
暗闇の中に並ぶ巨大な骨格標本や鉱物、化石。


佐原の偉人、伊能忠敬に関する展示ももちろんありました。
あの有名な測量の旅に使われた道具「象限儀(しょうげんぎ)」が展示されており、江戸時代の科学者が星と地図を頼りに、どれほどの距離を歩きながら日本を測ったのかを実感できました。

佐原の伊能忠敬記念館で見られるんですけどね。
でもやっぱり国立科学博物館に展示されるほどの偉業を成し遂げた人物。佐原の誇りです!
続いて訪れた「日本館」は、昭和6年(1931年)に建てられた歴史的建築物。
荘厳な外観は帝冠様式と呼ばれるもので、西洋建築の様式を取り入れつつ、屋根には日本の瓦を載せた、まさに和と洋の融合を象徴するデザインです。
この日本館は、平成20年(2008年)に国の重要文化財に指定されています。
理由はその建築的価値と保存状態の良さ。関東大震災の後に建てられた当時の鉄筋コンクリート構造としても貴重で、科学技術と美意識が融合した名建築です。

館内に一歩足を踏み入れると、白いドーム天井、ステンドグラスからの柔らかな光、重厚な石造りの階段。
これぞ重要文化財。
歴史ある建物内もまた博物館のままと言うのも趣と歴史を感じます。単なる建物というよりも「知の殿堂」。素材と構造、光と空気のバランスが見事に調和していました。
展示を見ながら、ふと子どもたちが口にした「これ、どうやって作ったの?」の一言。
それはまさに、学びの原点であり、私たちの仕事にも通じる探求の芽でした。
過去を知ることで、未来を考える。
古い建物に触れることで、今の建築を見直す。
そして、子どもたちの素朴な疑問が、次の世代の「つくる力」へとつながっていく。
そんな有意義なひと時を過ごせた一日でした。
+++